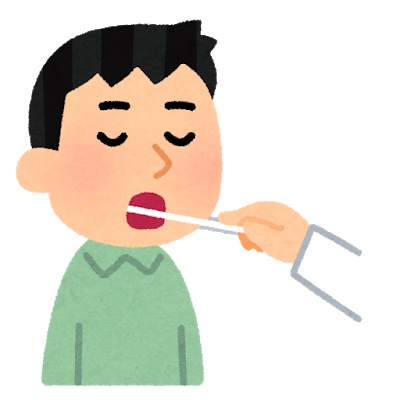2月にオープン以来、事前に申込いただいたお二人以外の問い合わせがなく、正直「どうしちゃったんだろう」という状況のリモワシェアハウス。
嬉しいことに次の週末に見学が入りました。
私だけでなく、今利用してくれてるハウスメイトたちも楽しみにしています。
駅から遠い、ということもあり、なかなか応募が進まないのが現状。
そんな中、日本語学ぶ人達を応援するシェアハウス「TOKYO SHARE FUNABORI(以下船堀)」は退去ラッシュ。
3月で卒業して帰国する人、遠くにある大学にいく人、それぞれの人たちが次のステップを目指して旅立ちます。
この3日間で8人が退去します。
一方で日本語学校に入学する予定だった人たちは、日本の緊急事態宣言発令とその延長によって、出国を具体的にスケジュールすることができず、補充がまだきいていません。
日本の緊急事態宣言の扱いが海外からみて、よくわからない仕組みなのかもしれません。
今行わなければならないのは、「感染拡大阻止」だというのが私の意見。
感染拡大防止のためには、「感染源の特定」と「感染後の対処」という2つの柱が必要。
これら施策の施行および実行管理は自治体にあるのが日本のルール。
自治体の動きは最近差がでてきたような印象をうけます。
例1で取り沙汰されるのが山梨県。
感染源の特定と感染拡大防止に具体的な行動をしていることがNHKで紹介されていました。
役所の人たちの労力は大変だと感じます。
なぜ他の自治体ではできていないのか。
乱暴な言い方ですが、Topの見識の低さで余計な労力が更に増しているのではないか、というのが個人的な印象です。
私なりの根拠は
です。。
まん延防止法、通称「まんぼう」が大阪などで適用されていますが、状況を定義しているだけで、具体的な感染源特定、感染防止の策が分かる形で公開されていないのが、今の一番の課題と感じます。
時短営業の要請とその補助金の仕組み。
これはこれで必要なことだと思うし、その仕組をつくるのは容易ではないことも想定できます。
でも台湾や山梨県でやっていることがどうして、大坂、宮城、東京でできないのか。
できない課題はなんなのか。
危機対応能力の低さを思いっきり露呈している今の日本。
その先頭に立つべき政治家の人たちは与党も野党も大いに反省して、外から学ぶ姿勢をもってこの社会の早期安定に向けて施策を講じてほしい、そう心から願います。
飲食店の時短営業要請しか行政の方針が見えないのが、はなはだ残念です。